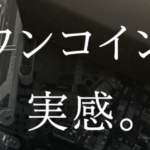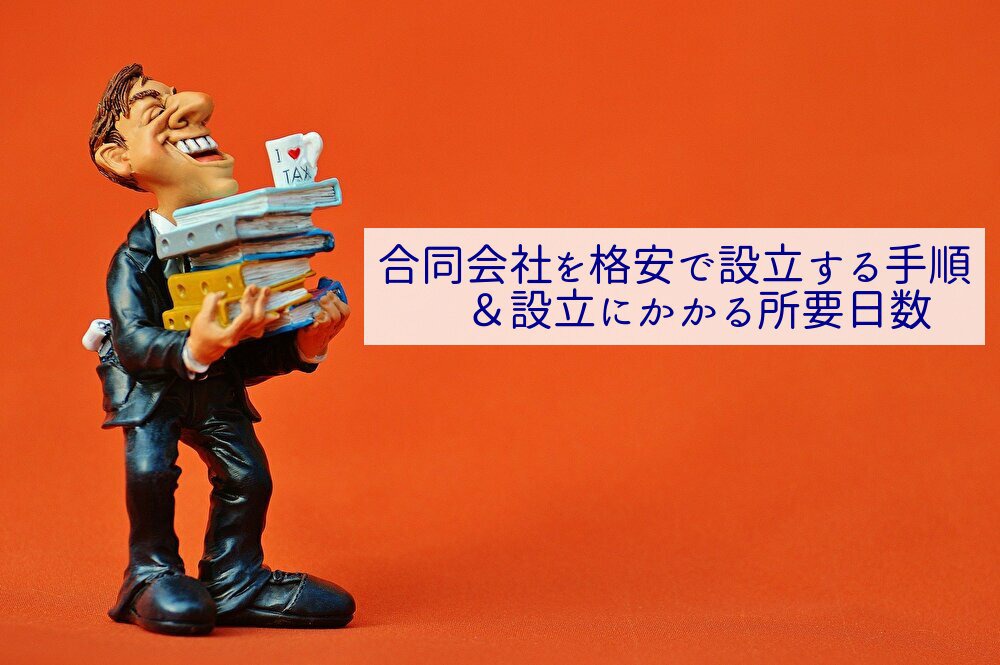
こんにちは。ペリカン(@Pelican0825)です。千葉県で大家業をしています。
私はもともと個人事業主だったのですが、事業収入がだんだん増えると、ある水準から一気に税率が重くなることに気づきました。
そして日本は、長期的な法人税率の軽減が大きな流れですから、将来的な税制面、事業継承など長期的に考えても、早めに「法人設立」しておくのが良いと考えました。
というわけで、私も2018年に法人を設立したということです。というわけで、本記事では「合同会社を格安で設立した方法」について詳しく解説してみたいと思います。
これから法人設立を検討されている方の参考になりましたら幸いです。
合同会社を選んだ理由
合同会社を選んだのは、なんと言っても設立費用の安さ(登録免許税が6万円)です。株式会社だと登録免許税が15万円に跳ね上がりますから、それだけで違いがあります。
また合同会社は決算公告も不要なので官報掲載義務がありません。役員の任期もないので更新費用(重任と言います)の費用と手間もかからないのもメリットです。
デメリットは、認知度が低いことと、上場できないこと、利益配分などです。詳細は省きますが、事業内容や目的に沿った会社形態を選ぶことが大切でしょう。
設立にかかる所要日数とは?

私の場合は、登記完了までズバリ「17日」かかりました。時系列では、以下の流れになります。
- 2月2日 法人設立サービス申込み(後述)
- 2月3日 代表個人の印鑑証明取得
- 2月4日 設立書類作成と印鑑発注
- 2月5日 CD-ROM購入(定款用2枚)
- 2月7日 印鑑が到着&登記申請書作成
- 2月13日 法務局へ登記申請書提出(=これが法人設立日になります)
- 2月19日 法人登記完了
法人印鑑が届いて登記書類を作って、すぐ提出すればもっと早くなります。
ペリカン家では、法人設立日を妻の誕生日と合わせたかったので少し申請を遅らせました。それがなければ14日間で登記完了まで行けたでしょう。
ですから通常でも、法人設立には、最短で2週間ほどかかるということになります。
合同会社を格安で設立した手順・掛かった費用は?
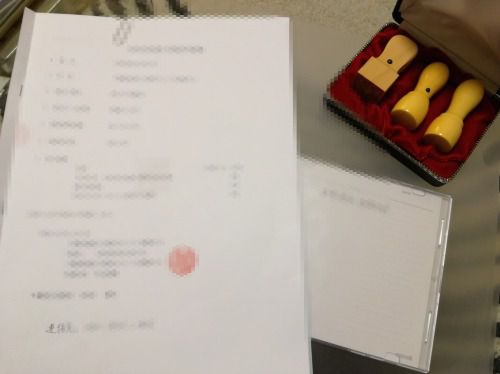
合同会社の申請手続きを、司法書士・行政書士にすべて代行してもらうと、もう少し早く設立可能です。
しかし先生への報酬として、合同会社は3万円〜6万円かかります。もちろん登録免許税6万円+印鑑作成が1万円程度は別途かかります。
私の場合は、「かんたん会社設立」というウェブサービスで、合同会社を設立しました。これは申請書類のフォーマットを使えるのと、セルフで登記できるよう詳しく手順を教えてくれるサイトです。
利用料金は6,000円くらいで良心的な値段でした。町の行政書士に直接依頼すると、数万円かかってしまうようなので、かなり節約できたと思われます。
このサービスが良かった点は、法人印鑑(別途1万円程度)もここで一緒に作成できることです。登記手順も分かりやすかったです。定款作成の際には簡単なアドバイスもしていただけて助かりました。
私のような、はじめて会社を設立するまったくの素人でも問題なく設立できました。かかった費用をまとめると、以下になります。株式会社だと20万円程度になるのでだいぶ割安です。
- 会社設立システム利用料 5,900円
- 印鑑3本セット 5,180円
- 印鑑ケース 1,680円
- ゴム印 2,940円
- ゴム印ケース 480円
- 登録免許税の印紙代 60,000円
- 印鑑証明・登記簿取得 3,150円
◆合計 79,330円
法人設立後にやっておくべき手続きとは?

会社の設立後にやらなければいけない届け出がけっこうあります。
まずは最寄りの法務局に行って、印鑑証明カードの発行をしてもらいます。これは無料でやってもらえて、カードは即日発行してくれるので簡単ですね。とりあえず法務局へレッツゴーです。
このカードを機械に差し込めば、法人の印鑑証明書と履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得することができます。ここまで来てやっと、法人設立した実感が持てますね。
その後は「役所まわり」と「銀行の口座開設」です。けっこうありますが、最寄りの管轄に1日で回ってしまえばいいでしょう。定款のコピーと法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明)が必要になります。
- 税務署への届け出
- 県税事務所への届け出
- 市役所への届け出
- 法人の銀行口座開設
- 年金事務所へ届け出
基本は上の5つの機関は必須になります。
なお、従業員を雇用した場合のみ以下にも届け出が必要になってきます。忘れないようにしましょう。
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 労働基準監督署
従業員を10人以上雇用する場合は、労基署に「就業規則」の届け出も必要になります。
社会保険の切り替えはどうする?
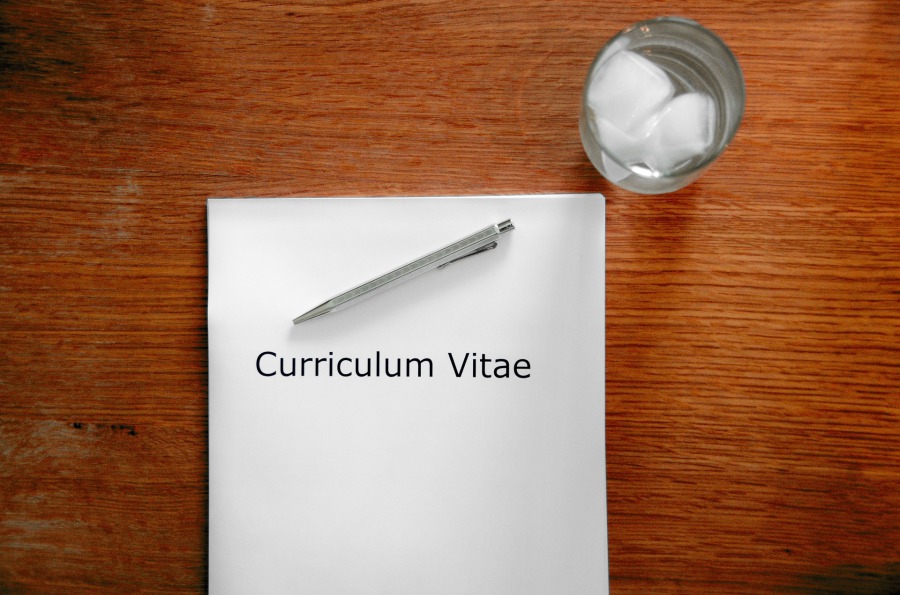
最後に、社会保険(年金・健康保険料)に関してです。
サラリーマンの方は会社で源泉徴収し、社会保険に加入しているはずです。サラリーマンの副業で売上がある場合は、確定申告している人が多いでしょう。
私のような個人事業主は、サラリーマン退職後に一旦、国保・国民年金に切り替えてしまっています。したがって、法人化した場合は年金事務所に行って、社会保険(厚生年金と協会けんぽ)に再度加入しなければいけません。
なお法人の役員報酬をいくらにするかによって、社会保険の金額が変わります。最初は給与を出しすぎると保険料が重くなりますし、会社のキャッシュフローも回らなくなるかもしれません。
サラリーマンをしながら副業や貯蓄に励んでおくメリットは、ここで出てきますね。
私の場合も、法人の自己資金(キャッシュ)を増やすために、役員報酬は最小限にして最初は賃貸業をやっていこうと考えています。役員報酬を少なくしすぎると、銀行受けは良くありませんが、事業実績をつくりながら徐々に黒字化させていこうと思います。
このあたりは会社の事業内容、資本金額、売上の目処、税金などによってトータルで判断して舵取りをしていく必要があります。
名実ともに、まさに「経営者」として判断していかなければいけないということですね。
▼私は法人の確定申告はセルフ申告しています。最近は便利なソフトが出ています。
▼セミリタイアして4周年が経過した私の収入の柱や、現在の心境について書いています。