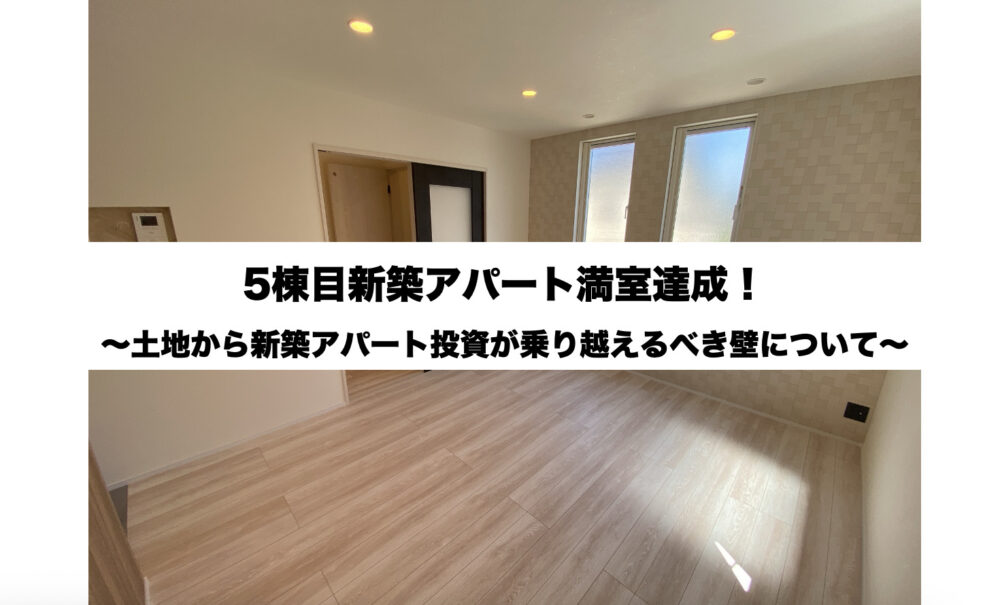
こんにちは。ペリカン(@Pelican0825)です。
このたび5棟目の土地から新築アパートが無事満室となりました!やっぱり新築アパートは何度建築しても、募集で埋まるかどうか毎回ドキドキするものです(笑)
ですから、土地から購入してゼロから作り上げた新築アパートが満室になったときは、立地・間取り・内装計画・募集条件などに間違いはなかったと実感できますから、格別のやりがいを感じることができます。
いつもお世話になっている建築会社のスタッフの皆さん、解体業者さん、仲介スタッフさんなど関係者の皆さんには本当に感謝ですね。
というわけで、ざっと5棟目新築の総工費・最終収支についてまとめます。今後の新築アパート投資が乗り越えるべき壁についても触れてみたいと思います。
5棟目の総工費・最終収支・内装仕様など
5棟目アパートの総工費と最終収支は、こちらです。
- 総工費:約4100万円
- 月額家賃:29万1,800円(=年350万円)
- 表面利回り:8.54%
まずは利回り8.54%というのが、地方で土地から新築やっている者としては少しさみしい印象がありますね。これまで建てた新築アパートを見返しても、3年前に建てた新築アパートは利回り10%超えていました。
その後も、2棟目(9.7%)、3棟目(9.0%)となんとか9%を超えましたが、昨年建てた4棟目(8.8%)となり、今回の5棟目はとうとう8%台半ばまで下落してしまいました。
今回、利回りが落ちた要因ですが、エクステリア費用が予算より100万くらい上振れたことが一番大きいです。くわえて水回りをバリューアップしたり内装にもお金を掛けたことで、全体では150万くらい当初予算からオーバーしました。

ただ今回良かった点として、内外装の仕様について新たな試みをすることができました。
主な仕様として、樹脂窓、エコカラット、界壁防音、風呂一坪サイズ、キッチン幅2100mm、対面キッチン、30年メンテ不要外壁&コーキング材など、自分で言うのもなんですがかなりグレードを高めましたから(笑)、10年くらいは余裕で賃貸マーケットで戦ってほしいものです。
ペリカンの投資戦略は「売却もできる立地で、できるかぎり長期ホールドする」というのを基本方針としているため、長く持っていて苦しい物件は買わないようにしています。
というのも、、、安く建てたら5〜10年回して売ったほうが、キャピタルゲイン(売却益)が取れて、またそれを元手に再投資していくと一番効率的に規模拡大できるよ!、、、なんてことを巷ではよく言われますが、これをすると今度は消費税課税業者になってしまい消費税が重くなる問題が出てきます。しかも短期間に反復売買すると、業法違反にも抵触します。
そう考えると賃貸業法人として基本活動するなら、長期ホールドしながら賃貸マーケットで戦っていけるスペックを備えた、競争力のある物件を建築するのが賢明でしょう。売却はあくまでサブ戦略で、積極的には考えないということですね。。
私が利回りを多少落としてでも、安普請な物件や狭小間取りのような物件を建てないのは、このような目線で物件取得・運営・出口をトータルデザインしているためでもあります。とは言え、収益性は高ければ高いほど運営も楽になり、売却もしやすくなりますから、収益性を諦めるわけにはいきません。
幸いにも次の6棟目(土地購入済み)は、土地が割安に取得できたので、また利回り9%達成を狙って間取りを現在練っています。6棟目は2LDKの間取りを入れた上で、利回り9%を達成したいと画策しています。!進捗はまた弊ブログでシェアしていきたいと思います。
全5棟の合計収支について
次に、これまで2022年〜2025年にかけて建築した新築アパート累計の収支についてまとめます。
以下が、全5棟の新築アパートの収支となっています。

まずBS的な部分ですが、購入総額(=総投資額)は1億8893万円となりました。これは土地+建物+外構費等のトータルの総工費になります。毎回2割くらい頭金を入れつつ返済も進んでいますので、現在の残債は1億3200万円ほどです。
次にPL的な部分では、満室時賃料は年間1742万円となり、平均利回りは9.2%です。毎月家賃は145万円ほど、ローン返済が月69万円ありますから、返済比率は47.5%ということになります。
ペリカンは、新築アパートの返済比率(家賃に対する毎月の返済割合)は50%以下が理想としています。それも最近は上昇傾向なのですが、新築は「家賃下落」すると一気に返済比率が上がっていくリスクがありますから、ここは要注意です。
今後も返済比率は上限55%程度をアッパーとして、自己資金も一部入れながら、安定経営を心がけていきます。
キャッシュフローは年間914万円ですが、そこから固都税・火災保険・広告料・空室ロスで家賃の12%(200万程度)は食われますので、税引前キャッシュフローで714万円くらい。減価償却による税金圧縮があるものの、法人税で毎年150万くらい持っていかれます。最終的な手残りは564万円くらいになります。
土地から新築アパート投資における今後の課題

土地から新築アパート投資において、いま我々が直面している一番大きな壁は、「利回りと金利の”イールドギャップ”が小さくなっている」という問題です。
つまり、収益性の確保が非常に厳しくなってきています!
思えば、日本はずっとゼロ金利政策・マイナス金利政策を取っていました。それが、2023年に日銀総裁が黒田さんから植田さんへ交代し、大きく金融政策を転換しましたね。
具体的には、2024年3月からはマイナス金利解除、同年7月から政策金利0.25%となり「金利がある世界」に戻りました。2025年1月から政策金利が0.5%にアップしています。皆さんの住宅ローンやアパートローンも、金利が0.3〜0.5%くらい上がってビックリした人も多いことでしょう。
こうした金利上昇により儲けの源泉である「イールドギャップ」が取りづらくなっている点について、ペリカンは2つの観点で戦っていきたいと考えています。
いろいろ賛否が分かれる点もあるかと思いますが、一つの意見として参考にしてください。
1.都心部より「地方エリア」のほうが投資としての歪が大きい
投資においては「エリア選定」がポイントになってきますが、私は都心部より地方エリアのほうがポテンシャルが高いと考えています。これは地方都市に住んでいる私のポジショントークに聞こえるかもしれませんが、本当にそう思うのです。
たとえば関東エリアだと東京や横浜などの「都心部エリア」で勝負していくと、資金力がかなり必要になります。なぜなら、都心エリアで優良物件が出て早押しボタンで買い付け一番手を取れたとしても、最終的には現金買いの業者に持っていかれる可能性はけっこう高いです。つまりキャッシュがそれなりにないと、1番手を確保できません。
そして、なんとか土地をグリップできたとしても、おそらく東京の都心部では利回り6%台くらいがせいぜいだと思います(都内で新築7%出るエリアは郊外が多くなります)。すると、今は金利1.5%で融資が引けたとしても、将来的に2%台半ば〜3%弱になったとき、どんどんイールドギャップが小さくなり苦しい収支になっていくことが予想されます。
もちろん都心部の場合には家賃アップして、売却時も高く売れる可能性もあります。しかし、収支が苦しくて長く持てなければ、けっきょくローンの元金返済が進まないので、大したキャピタルゲインは得られません。おそらく、購入時に割安に買った含み益を現金化する以上の効果はないでしょう。30年〜35年融資を引いていたら、なかなか元金が減りませんからね。
都心部は、レバレッジをかけて投資して得られる利益より、リスクのほうが大きくなっているとも言えます。これは考えてみれば、そうなのです。株式投資でもみんなが群がる人気銘柄は、都心部の物件と一緒です。
ほとんど「投資の歪」が生まれにくいので、自分だけが儲かるタイミングや価格でその銘柄(物件)を買える確率は非常に低いです。買うとするなら、かなり特殊なルートで仕入れるか、自分のキャッシュポジション自体を上げて、向こうからお話が来るようなステージまで自分が上がらないといけません。
一方で、地方エリアだとまだ土地から新築でも8%〜9%を実現することは十分可能です。そのくらいの利回りがあれば、金利1%台なら運営は余裕がありますし、金利2%台になっても頭金を1〜2割入れて対応すれば収支は回ります。問題は、割安な土地が手に入るかどうかですが、都心部よりは争奪戦もマイルドではないでしょうか。
以上より、都心部の利回り6%台というのは、金利上昇局面においてはかなり苦しくなっていくことが予想されます。こういう物件を35年融資など長期ローンで無理やりキャッシュフローを出したとしても、家賃が落ちたり、金利がさらに上がるようなことがあれば持ち切ることはできないでしょう。もちろん、資産保全としての目的なら良い投資先となります。

2.金融機関との関係性の醸成していくことに注力する
金利上昇の2つ目の対策は、お付き合いする金融機関の幅を広げ、関係性を醸成しておくことだと考えています。
けっきょく、金利上昇と言ってもA銀行とB銀行とC信金では、各金融機関で融資条件というのは違います。これはやはり金融機関どうしも競争があるということですね。優良な貸出先には、どこの金融機関も融資をしたいものです。
そういう意味では、決算書を磨いておくことが一番大事ですね。BS・PLともどこの金融機関が見ても、良い決算書である必要があります。そしてお付き合いする金融機関も1〜2行だけでなく、やはり最低3〜4行あると良いでしょう。
ペリカンも現在は地銀1行、信金2行とのお付き合いがありますが、もう少し金融機関の幅を広げておかなければいけないなと考えています。金融機関は一見さんですぐ取引スタートは難しいので、最初はリフォーム資金や保証協会付き融資など、小さな融資実績からでもスタートして、徐々に大きな取引に結びつけていくのが良いでしょう。
私も毎回プロパー融資を申請する際には、金融機関から言われた金利で申し込みしていましたが、新築も6棟目になってきたので、今後は金融機関どうしで競ってもらい、少しでも有利な金利で借入ができるよう進めたいと思います。なんとか金利1%後半〜2%台前半くらいで踏みとどまれれば、土地から新築が成立するイールドギャップは取れますからね。
不動産業界は「金利上昇」というものすごい逆風が吹き荒れていますが、私もどうにかイールドギャップを死守しつつ、土地から新築アパート投資を継続したいと考えています。
だって不動産投資の良いところは、耐えて所有していれば、多少キャッシュフローは悪化しても、ローン返済は着実に進んでいくところでもありますからね。まさに「時間を掛けること」こそ、不動産投資で成功する最大のポイントなのですよね。
資産拡大する方法に近道など無いということだろうと、自分の中では結論付けています。
以下、関連記事です。
▼新築アパートの出口戦略についての私見です。
▼法人化は拡大のためのポイントです。法人化のメリットについて纏めています。








